荒井勝喜首相秘書官が更迭される事となった。性的少数者や同性婚に対する差別的な発言が問題視された事によるものだ。公職の人間はマイノリティに対する発言がどこまで許されるのか考えてみた。
荒井勝喜首相秘書官の更迭の詳細
岸田文雄首相は4日朝、性的少数者や同性婚をめぐって差別的な発言をした荒井勝喜・首相秘書官について、記者団に「言語道断だと思っている。厳しく対応せざるを得ない発言だ。進退を考えざるを得ない」と述べ、更迭する考えを明らかにした。
荒井氏は3日夜、首相官邸で記者団の取材に、性的少数者や同性婚をめぐって「隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」などと発言。その後「やや誤解を与えるような表現をした。撤回する」と釈明したが、首相周辺による差別的な発言に批判が相次いでいた。
荒井首相秘書官を更迭へ 性的少数者への差別発言に首相「言語道断」
要するに荒井勝喜首相秘書官がオフレコの場で性的マイノリティや同性婚に関して差別的な発言があり、度を越していたのでマスコミが報じたという事だ。内容的にはこれを公職が言ったなら更迭はやむなしという感じ。
ただ私は個人の意見は尊重されるべきだと思っている。特定個人や団体での誹謗中傷でない限り。
荒井氏の発言は撤回されているが、そもそもの内容は自然に口から溢れてきたわけで本心だと言っていいだろう。その意見自体は自由だと思う。
例えば「黒人を見るのも嫌だ、隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」と発言した人がいたとする。世間からは人種差別だと叩かれるはずだ。
しかしこれが「かつて黒人から性被害に遭った事があり、それ以来目にしただけで身体が固まってしまう。黒人全員が悪いわけではない事は当然理解しているが、感情はどうしようもない」と言われたらどうか。私はそれを非難できない。
なんの理由もなくヘイトを撒き散らしたり権利侵害を迫ったりするならそれは差別だと思うが、個人的な感情や思想は当然個人の権利に収まるものだろう。少なくともその発言の理由くらいは推し量るなりしてもいいはず。
ただしそれは公職の人間には適用されないと考える。公務員は国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないからだ。だから個人的な感想や見解などはオフレコだろうと語るべきではなかった。「匿名のとある政治秘書官」的なアカウントで語るべきだった。
本田氏のツイートは論旨には同意だ。実務能力と関係ないところで一発レッドカードはむしろ社会のどこかに皺寄せがいくとも考えられる。
ただ公職の人間が実名で発言する以上「その思想が政策等に反映されたり世論が影響されては困る」と国民が思うのもまた当然と言える。これはもう力学的に仕方ない事。まして今回は好き嫌いだけでなく「社会に与える影響が大きい」「秘書官室もみんな反対する」なんて言ってしまっている。
なので公職の人間はそもそも個人の感想なんて言うべきじゃないと思う。「とある政治秘書官」くらいの匿名性を持ったアカウントでないと紐付けされてしまうはず。
よく「こちらはプライベートアカウントです」みたいなアカウントを見るが、投稿内容を分ける意味で有効とはいえ、中の人の同一性が周知であれば問題発言は属性と紐づけられてしまう。「個人的な感想だから」は通らない。
その属性が公職なら資質を疑問視され、企業なら不買され、それが株式会社なら株主から怒られる。これもまたどうしようもない力学的な事だと思う。
オフレコの存在意義や運用がわからない
もう一つ、オフレコに関して。これがよくわからない。言葉としては意味も使い所もわかるが、なぜマスコミ内に概念として使われているのか、なぜその運用まで詳しく決まっているのか。
筋的に言えば公開しないと約束した前提で話を聞いたなら約束は守らなくてはいけないのが社会的な規範なので公開は論外だと思うが、そもそも今までも「聞いた話が重大なので約束を破って公開します」という流れはあった。
過去に政権幹部らのオフレコ発言が問題になったケースでは、02年に福田康夫官房長官(当時)が、オフレコの記者懇談で「非核三原則」見直しに言及▽09年に漆間巌官房副長官(当時)がオフレコの記者懇談で、西松建設の違法献金事件の捜査に関し「自民党議員には波及しない」と発言▽11年に鉢呂吉雄経済産業相(当時)が、福島第1原発を視察した後、衆院議員宿舎で記者団に「放射能をつけたぞ」という趣旨の発言▽11年に当時の沖縄防衛局長が飲食店での記者懇談で米軍普天間飛行場の辺野古移設に関して性的な表現を使って発言――などがあった。
オフレコ取材報道の経緯 性的少数者傷つける発言「重大な問題」
だったらそんなシステムはそもそもなくていいんじゃないだろうか。「オフレコの記者懇談」という仕組みが用意されている事自体がわからない。聞いた事は全てマスコミ各社が出す出さないを判断します、取材を受ける人間はその前提で発言します、が自然だと思う。
「今のはオフレコでお願いします」ならわかるんだよね。それは「今のは本意ではないので撤回します」という意味合いにとれるので。誰にでも失言はあり、訂正の機会も与えられるべき。そうではなく「これから話す事はオフレコでお願いします」の場がまかり通っているのが不思議でならない。
マスコミは守れない約束はするべきではないし、公職についている人は職務と関係ない個人的な発言を慎むべきだとシンプルに思う。
記事内に出てきた関連リンク↓
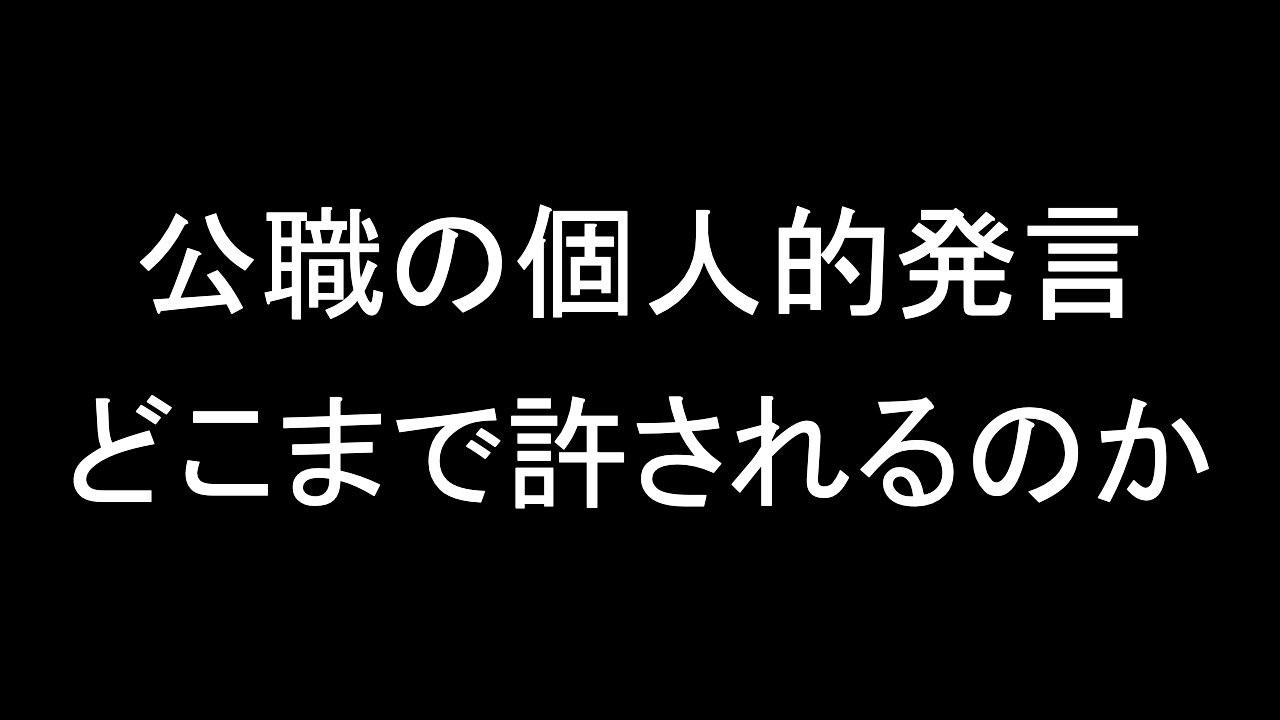
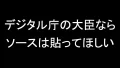
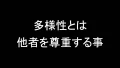
コメント